
Special-column
開放医療への想い
Special Column
「生きていくことのつらさを、
少しでも分かち合いたい。」

ソフトな容貌、飾り気のない物言い。誰にもおだやかな印象を抱かせます。しかし、まなざしの奥には、いわくら病院の開放医療を、どんな反対にあっても挫けずに推し進めてきた強い意志がうかがえます。感受性ゆたかな少年時代、恐ろしくてたまらなかった「死」と、「人はなぜ差別や偏見をもつのか」という二つの疑問に、医療の世界でなんとか答えを出したいと願い、何としてでも実現させたかったのが開放医療でした。
「病気でつらい上に、なんで偏見を持たれなあかんねん」「自分よりつらい人がいたら、分かちあわないかんのと違うの」シンプルすぎるほどの思い。
それは徐々にまわりの人びとの心を動かし、やがて「いわくらには鉄格子はなくて、情がある」と言われる、「いわくら型民主主義」の医療体制を多くの人達と共に作り上げていきます。いわくら病院とともに歩んできた歴史を、当時赴任した6人の医師の1人である崔医師が語ります。
少年時代
 死と差別、
死と差別、
二つの大きな悩み

私の父は牧師でした。だから私も高校2年までは神学部に行くと決めていました。しかし、シュバイツァー博士も医者をしてから牧師になったのだから、自分も博士にならって医師の経験を積みたいと、医学部をめざすことにしました。
実は10歳ぐらいから、私には死に対する恐怖が過剰なほどにありました。きっかけは近所のおばあちゃんの死です。私はそのおばあちゃんに可愛がってもらっていたのですが、お葬式の列が長く続くのを見て、言いようのない恐怖にとらわれました。人はみんな死ぬ―それは体中の力が全部抜けてしまうほどの虚脱感でした。「死ぬことが決まっているのに、人はなんのために生きるのだろう」。思えばその時、心の深淵を覗き込んでしまったんですね。それまで腕白坊主だった私は、それ以来どこか翳りのある少年になりました。
また、牧師の息子としてそれなりに正義感も強く、誇り高かった私は、世の中にいわれのない差別が存在することにも早くから気づいていました。その人物の中身に関係なく、生まれた場所や性別、見た目など、世間は様々な要因で差別をします。それを受けた本人がどれほど傷つくかは想像がつくことなのに、差別や偏見はなくなろうとしません。なぜなんだろう。少年の私には難しすぎる疑問でした。心の医者になろうと思ったのも、そういった体験が関係しているのかもしれません。
たたかいの時
 患者さんの尊厳を
患者さんの尊厳を
取り戻すために

1970年、私はいわくら病院に医師として赴きました。1952年に開設されたいわくら病院は、伝統ある精神科の病院でしたが、労働運動を共に戦っていた医師全員が辞め、院長一人が診療にあたるという異常な事態を迎えていました。そこに私は他の5人の医師とともに就職したのです。
この医師たちが揃って医療現場の改革を訴えました。当時日本でも少しずつ取り入れられつつあった開放医療を志したのです。その頃のいわくら病院は、強力な看護力で一定の評価を得ていました。しかしそれは看護師のみでなく、資格を持たない看護助手たちが、恐怖によって患者さんたちを支配し、無理矢理言うことを聞かせるというものでした。言葉は悪いですが、監獄のような状態が当たり前の世界だったのです。この看護人たちは地元出身の人びとで、経営者との血縁関係であることも多く、よそからやってきた医師や看護師たちに有無を言わせない体制を作り上げていました。彼らにとって医師や看護師は3、4年で辞めてしまう、通行人も同然の存在でした。
そんな中、私たち6人は、治療の主体性は患者側にあること、その人権はあくまで尊重され、患者さんは人間的に扱われなければならないことを訴え、それまでの病院のやり方をすべて否定していきました。当然院内は大混乱、特にポッと出の医師たちに、自分たちが築いてきたものを壊されると感じた看護人たちの反発はすさまじいものがありました。「きれいごとを言って、どうせ3年たったら辞めるやないか」。彼らはそう主張し、危険な目に遭っても助けてやらないぞと脅された医師や看護師もいました。
この時期はつらかった。文字通り、命を削るような日々でした。5人の仲間がいなかったら、きっと逃げ出していただろうと今でも思います。
試練の時
 本当の開放治療を
本当の開放治療を
めざして

闇の中に一筋の光が見えたのは、開放医療に取り組みだして数年が過ぎた頃でした。いまも忘れられないエピソードがあります。 1972年から3年ほど、私は男性の準閉鎖病棟に勤務していました。毎朝のように数人の患者さんが、真っ青な顔をして私に食ってかかってくる状態が続き、大変なストレスを抱えていました。出勤拒否に近い心情で、休みの日には決して洛北には足を向けず、出勤の朝には病院が近づくと心拍数・血圧ともに上がるのがわかりました。 1年ほど経った頃のある夕方、医局に電話がかかってきました。ちょっと病棟に来てくれないかというのです。なんだろうと思いつつ行ってみると、そこでは看護人たちが、地元でとれたマツタケを焼きながら寛いでおり、「先生も食べえな」と誘ってくれたのです。そして、じつは患者さんが私に食ってかかっていたのは、自分たちが患者さんに「様々な制限を与えているのはあの医者だ」と教えていたからだ、と打ち明けてくれました。看護人たちも、ただ反発していたのではなく、私たちが本当にやる気かどうかをじっと見ていたのですね。こうした出来事をきっかけに、少しずつ私たちは思いを共有できるようになり、ついに手をたずさえて病棟の鉄格子を外すことができました。私たちにとってはベルリンの壁を壊すのに匹敵する、記念すべき出来事でした。しかし、開放病棟に向けての闘いは、むしろそれからだったのです。
急に鉄格子を外された患者さんたちは、どうしていいかとまどっていました。それはそうです。これまで制限されるのが当たり前だったのを、急に「主体的に、自分で考えて行動してください」と言われても、なかなかできるものではありません。患者さんたちは一日中ボーっとしていることが多く、「ぶらぶら開放」「ゴロゴロ開放」などと非難されました。
また、一人で外出できるようになった患者様が、近隣で迷惑行為をするという問題にも悩まされました。私たちは、患者様の自由を確保したと思っていましたが、一方で地域の人びとに我慢を強いていたのです。たまりかねた地域の方たちの不満が爆発したとき、それは地域の人びとの理解が足りない、差別だ、と怒った職員もいました。しかし、辛抱強く話し合いを続ける中で、権利には義務があり自由には責任があるということ、そして病院のスタッフも患者様も地域の一員であるという意識が育っていき、信頼関係が徐々に築かれていきました。また、自主的に動くことの楽しさを患者様に知ってもらうよう、レクリエーションやイベントなどを通じて働きかけました。地道な努力の積み重ねによって、ようやく体制が整ってきたなと感じたのは、90年代も後半になってのことでした。
いわくらのこれから
 あたたかい
あたたかい
社会のために
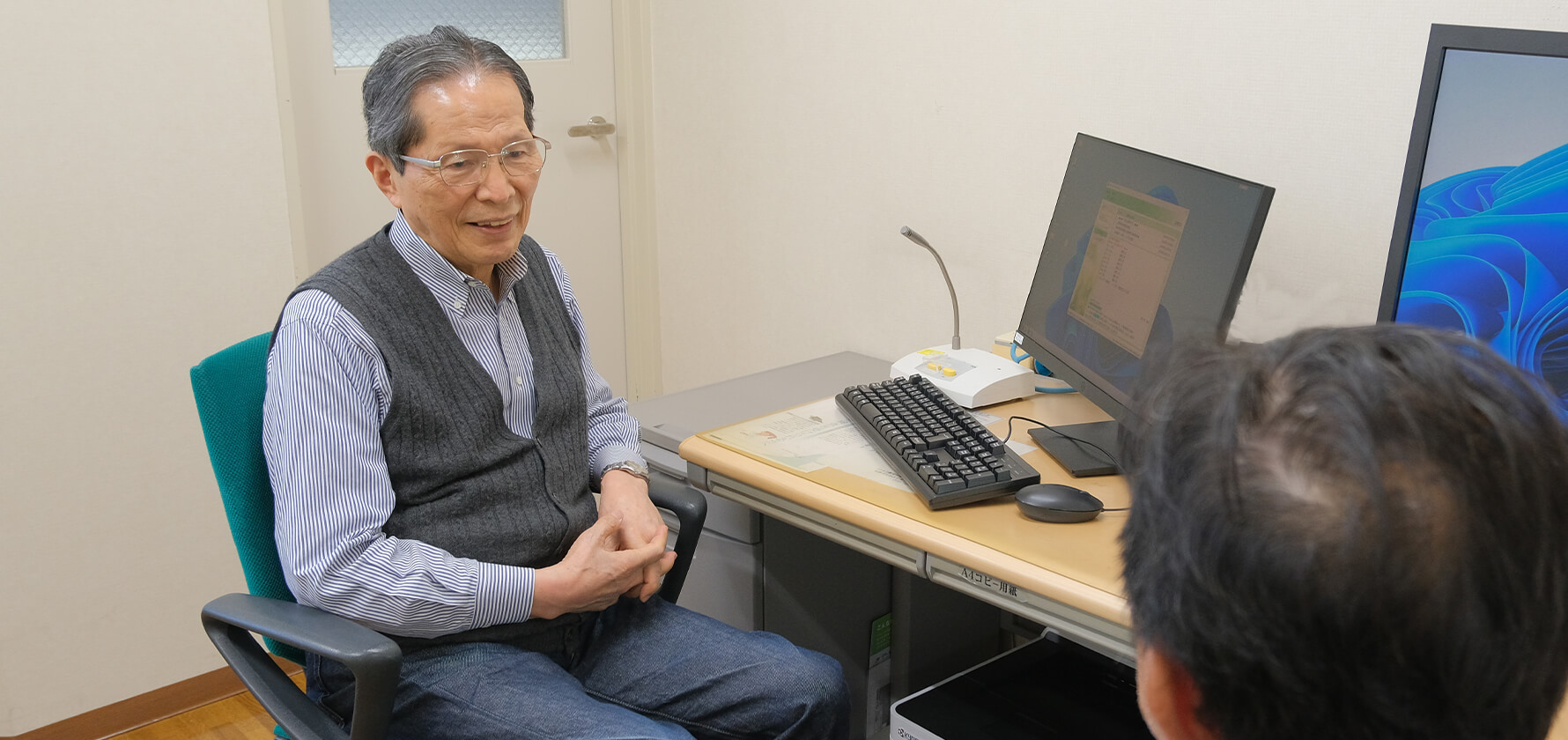
いま、いわくら病院では認知症疾患治療病棟を除いて、開放病床が実現しています。入院中の患者様が、自由に外に出られるのみでなく、外の方たちも自由に入れる病院です。退院した方が外来の日に病棟を訪ね、入院している友人と情報交換をしたり、おしゃべりを楽しんだりすることもできます。見学もおおいに歓迎です。百聞は一見にしかず。来られれば、一般の病院と雰囲気が変わらないこと、そして患者様が“こわい方”でも“得体の知れない方”でもないことが、すぐにわかってもらえるでしょう。
実際いわくら病院の夏祭りは、地域の方が大勢来られる人気行事。そのような機会に、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。ようやくここまで来ましたが、私の実感としてはまだ5合目か6合目。なぜなら社会に精神病の患者様を受け入れる土壌はまだまだ育っておらず、退院しても行くところがないため、病院生活を余儀なくされる方たちが大勢おられるからです。いわゆる「社会的入院」の方たちです。また、日本全国で、開放病棟はまだ50%に達していません。半分以上の病棟で、患者さんたちはいまだに鉄格子と鍵に管理された生活を送っているのです。
生きていれば誰しもつらいことがあります。にもかかわらず、つらい上にもつらい思いをしている方たちをはじき出して、私たちは本当にしあわせなのでしょうか。そんな思いがいつも心の中に生じます。競争社会の中で、子どもの頃から勝ち負けばかりが問われる昨今ですが、世の中にはどうしようもないこともあるし、歯をくいしばっても、なかなか思うように生きられない方がいるのです。そのことを知り、お互いをもう少し温かい目で見られるようになれば、人間はもっとやさしくなれるのではないでしょうか。
少年時代に感じた「人はなぜ生きるのか」そして「差別がなぜあるのか」というという疑問への答えはま出ていません。それを探すことそのものが、生きることなのかもしれませんね。これからもこのいわくらという場所で、静かに、熱く、自らの信じる道を歩んでいきたいと思います。

いわくら病院元院長
崔 秀賢
さい・しゅうけん
1943年東京生まれ。
1968年大阪大学医学部卒業後、
大阪回生病院内科研修医、
大阪大学医学部精神科研修医を経て
1970年医療法人稲門会いわくら病院勤務。
1998年よりいわくら病院院長。
2016年3月院長を退任。








 採用情報
採用情報